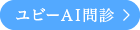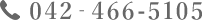内科について
 風邪やインフルエンザなどの症状でもある、発熱や頭痛・喉の痛み・腹痛・悪心・嘔吐などの急性症状をはじめ、胃腸炎や胃十二指腸潰瘍・気管支炎・咳・喘息・発疹・呼吸困難・アレルギーなど、一般的な症状や疾患に対応しております。また、生活習慣病と言われる高血圧や糖尿病・脂質異常症・高尿酸血症・骨粗鬆症など慢性疾患にも対応しております。また、不眠やストレスなどからくる体調不良や、なんとなく具合が悪いけれど何科を受診すればいいのか分からない方なども、まずは当院までご相談ください。
風邪やインフルエンザなどの症状でもある、発熱や頭痛・喉の痛み・腹痛・悪心・嘔吐などの急性症状をはじめ、胃腸炎や胃十二指腸潰瘍・気管支炎・咳・喘息・発疹・呼吸困難・アレルギーなど、一般的な症状や疾患に対応しております。また、生活習慣病と言われる高血圧や糖尿病・脂質異常症・高尿酸血症・骨粗鬆症など慢性疾患にも対応しております。また、不眠やストレスなどからくる体調不良や、なんとなく具合が悪いけれど何科を受診すればいいのか分からない方なども、まずは当院までご相談ください。
このような症状はありませんか?
- 発熱
- のどが渇く
- のどの痛み
- 吐き気
- 嘔吐
- 便秘
- 下痢
- 咳
- 痰
- 息切れ
- 動悸
- 疲れやすい(易疲労性)
- やる気がない
- イライラする
- 食欲がない(食欲不振)
- 食欲がありすぎる
- 体重減少
- 体重増加
- 膨満感
- 寒がり
- 暑がり
など
よくある病気
糖尿病
 血液中の血糖値が高い状態が長く続くと、糖尿病になります。血糖値を正常にコントロールするインスリンの分泌量が少なくなり、機能が低下すると、血糖値が高い状態が続きます。糖尿病は、初期症状がほとんどないまま病気が進行します。また、初期の糖尿病と診断された場合でも自覚症状がほとんどないため、正しい病気への理解がないと治療を怠ってしまう傾向にあります。適切な治療を行わないと、次第に血管を傷つけ血流が滞り、網膜症(糖尿病網膜症)や腎不全(糖尿病腎症)、末梢神経障害(糖尿病神経障害)などを招くほか、脳卒中や心筋梗塞などを発症しやすくしてしまいます。重篤になると失明や足の切断、人工透析などが必要となるなど、生活に大きく支障を及ぼす事態となってしまいます。当院では、糖尿病専門医による適切な検査及び治療を行っております。血糖値の異常が指摘されたら、お早めにご相談ください。
血液中の血糖値が高い状態が長く続くと、糖尿病になります。血糖値を正常にコントロールするインスリンの分泌量が少なくなり、機能が低下すると、血糖値が高い状態が続きます。糖尿病は、初期症状がほとんどないまま病気が進行します。また、初期の糖尿病と診断された場合でも自覚症状がほとんどないため、正しい病気への理解がないと治療を怠ってしまう傾向にあります。適切な治療を行わないと、次第に血管を傷つけ血流が滞り、網膜症(糖尿病網膜症)や腎不全(糖尿病腎症)、末梢神経障害(糖尿病神経障害)などを招くほか、脳卒中や心筋梗塞などを発症しやすくしてしまいます。重篤になると失明や足の切断、人工透析などが必要となるなど、生活に大きく支障を及ぼす事態となってしまいます。当院では、糖尿病専門医による適切な検査及び治療を行っております。血糖値の異常が指摘されたら、お早めにご相談ください。
脂質異常症
血液中の脂肪分(コレステロールや中性脂肪)数値が高すぎる、または少なすぎる状態が脂質異常症です。血中の中性脂肪やLDLコレステロールが高すぎる、またHDLコレステロールが低すぎると、動脈硬化を起こします。脂質異常症は、自覚症状がほとんどないまま動脈硬化が進み、血管を狭窄・閉塞させて心筋梗塞や脳梗塞など血管疾患を引き起こしてしまいます。過食や過度の飲酒、喫煙、運動不足など不規則な生活習慣が要因となり発症しますので、栄養バランスのとれた食事習慣をはじめ、禁酒や運動習慣など、生活習慣の改善を図ることが大切です。また、早期発見のためにも定期検査を受けることをお勧めします。
高血圧
 血圧とは、血管にかかる圧力を言います。血圧が高い状態が高血圧ですが、緊張によって数値が変化することもあるため、一般的に診察室で計測した場合は140/90mmHg以上、家庭血圧が135/85mmHg以上の状態を高血圧とします。
血圧とは、血管にかかる圧力を言います。血圧が高い状態が高血圧ですが、緊張によって数値が変化することもあるため、一般的に診察室で計測した場合は140/90mmHg以上、家庭血圧が135/85mmHg以上の状態を高血圧とします。
高血圧が長く続くと、次第に動脈硬化が進み、心筋梗塞や脳卒中・脳梗塞・狭心症・腎臓病などを引き起こし、心機能が低下すると心不全を起こす恐れがあります。高血圧の治療は、まず食事習慣をはじめとする生活習慣の改善を行います。減塩に気を付けたり、適切な運動などを行ったりして減量を心がけます。生活習慣の改善を図っても効果が得られなかった場合は、薬物療法を行います。これらの治療を行いながら、適切な血圧を維持していきましょう。
高尿酸血症(痛風)
尿酸は、水に溶けにくい性質から血液中では尿酸塩として滞在します。尿酸が過剰になると、体内で結晶を生成し足の親指付け根などに形成して「痛風」と呼ばれる病気を発症します。このように、血中の尿酸値が通常よりも高い状態を高尿酸血症(痛風)と呼びます。主な症状として、強烈な痛みと腫れ、発赤などの痛風発作が現れます。さらに、腎臓に結晶を形成することがあり、これが腎臓結石となります。
高尿酸血症の原因となる尿酸は、プリン体を大量に摂ることで生じます。プリン体は、レバーやビール、魚卵、いわし、えび、かつお、干し椎茸などの食品に含まれています。このため、プリン体を多く含む食品の摂取には十分に気を付けなければなりません。
高尿酸血症の治療は、生活習慣と薬物療法を行います。まずは、これまでの食事習慣を見直し、カロリー制限を行うと同時に適度な運動などで減量を図ります。肥満を防ぎ、痛風関節炎など必要に応じて非ステロイド抗炎症薬などで治療を行っていきます。
花粉症
 春や秋など、花粉の飛散時期に起こるアレルギー疾患として挙げられるのが花粉症です。春にはスギやヒノキ、秋にはブタクサなどを始めとするアレルゲンが存在します。
春や秋など、花粉の飛散時期に起こるアレルギー疾患として挙げられるのが花粉症です。春にはスギやヒノキ、秋にはブタクサなどを始めとするアレルゲンが存在します。
主な症状として、鼻水や流涙、充血、皮膚の痒み、倦怠感、不眠、微熱などが現れます。花粉症の症状が酷くなると、日常生活に支障を及ぼしてしまうほど辛い症状となります。
当院では、アレルギー検査を行うとともに、舌下免疫療法を実施しております。花粉の飛散時期にアレルギー症状に悩まされることなく穏やかに過ごせるように、花粉シーズンの前に適切な治療を開始しておきましょう。