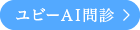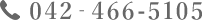糖尿病内科について
 糖尿病とは、血糖値(血液中のぶどう糖)は高い状態が長く続く病気です。私たちの身体は、食事をすることで血糖値が上がります。通常、血糖値が上がると、膵臓からインスリンが分泌されて、正常にコントロールされて血糖値を正常に戻します。このインスリンの分泌量が減ったり、働きが低下したりすると、血糖値が高い状態が長く続いてしまいます。長期間、血糖値が高い状態が続くと、全身の血管が傷ついてしまい、重篤化すると失明や足の切断、腎臓病などの合併症を引き起こしてしまいます。糖尿病は、初期の自覚症状がほとんどないまま病状が進み、脳卒中や心筋梗塞などを起こす動脈硬化を進行させてしまいます。「サイレントキラー」とも呼ばれるように、QOL(生活の質)を大幅に低下させてしまう病気です。当院の糖尿病内科では、糖尿病専門医が糖尿病の検査・治療などを行っています。
糖尿病とは、血糖値(血液中のぶどう糖)は高い状態が長く続く病気です。私たちの身体は、食事をすることで血糖値が上がります。通常、血糖値が上がると、膵臓からインスリンが分泌されて、正常にコントロールされて血糖値を正常に戻します。このインスリンの分泌量が減ったり、働きが低下したりすると、血糖値が高い状態が長く続いてしまいます。長期間、血糖値が高い状態が続くと、全身の血管が傷ついてしまい、重篤化すると失明や足の切断、腎臓病などの合併症を引き起こしてしまいます。糖尿病は、初期の自覚症状がほとんどないまま病状が進み、脳卒中や心筋梗塞などを起こす動脈硬化を進行させてしまいます。「サイレントキラー」とも呼ばれるように、QOL(生活の質)を大幅に低下させてしまう病気です。当院の糖尿病内科では、糖尿病専門医が糖尿病の検査・治療などを行っています。
糖尿病の原因
糖尿病は、1型糖尿病・2型糖尿病の2種類に分類され、さらに妊娠中の女性に見られる妊娠糖尿病があります。それぞれ、発症の原因が以下のように異なります。
妊娠糖尿病
妊娠中の女性に見られる、まだ糖尿病に至っていない軽度の糖代謝異常の状態を妊娠糖尿病と言います。胎盤から発出されるホルモンの影響で、インスリン機能が低下することが原因です。なお、明らかに糖尿病とされる場合は、妊娠に関係なく糖尿病として診断し、治療を行います。
糖尿病の症状
- 疲れやすい(易疲労感)
- 頻尿
- 手足の感覚が低下する
- 眼がかすむ
- 皮膚が乾燥する
- 空腹感
- 皮膚の傷が治りにくい
- 喉が渇く
- 突然痩せる
- ED(勃起不全)などの性機能障害
- 手指がチクチク刺すような痛みがある
- 便秘
- 下痢
など
足の裏が熱いのは糖尿病?
足の裏が熱い原因としては、以下のような状態が考えられます。さまざまな原因が考えられますが、糖尿病でも足の裏が熱くなることがあります。気になる症状がありましたら、お気軽に当院までご相談ください。
糖尿病
足の裏が熱いと感じる症状は、糖尿病の合併症である「糖尿病性神経障害」が原因のひとつとして知られています。長期間にわたって血糖値が高い状態が続くと、足先や手先など体の末端にある神経が障害を受け、しびれや感覚の鈍さ、そして「焼けるように熱い」「ジンジンする」といった不快な感覚が現れます。特に夜間や安静時に強く出やすいのが特徴です。この場合、怪我ややけどに気づかず悪化させてしまうリスクもあるため注意が必要です。
血流障害
糖尿病に限らず、動脈硬化や末梢動脈疾患などによって足への血流が悪くなると、足裏に熱さや痛み、逆に冷たさを感じることがあります。これは、血液がうまく循環しないことで神経が異常な反応を示しているためです。長く歩いたり立ち続けたりすると症状が強まることが多く、場合によっては足がだるくなる、色が変わるといった変化も伴います。
足の使いすぎや炎症
一日中立ち仕事をしたり、長時間歩いたりすると、足裏に負担がかかって炎症を起こすことがあります。このような場合、足裏の筋肉や腱にストレスが加わり、その部分が熱を持つことで「足の裏が熱い」と感じるのです。特に自分の足に合っていない靴を履いていると悪化しやすいため、靴選びも重要になります。
栄養不足(ビタミン欠乏)
神経の働きにはビタミンB群(特にB1、B6、B12)が深く関わっています。これらが不足すると、神経の伝達がうまくいかなくなり、しびれや灼熱感といった症状が出ることがあります。偏った食生活や過度の飲酒が原因で不足する場合もあり、栄養バランスの見直しが必要になることがあります。
ホルモンや代謝の異常
甲状腺の病気やホルモンの異常も、足の裏の熱さにつながることがあります。これは代謝が過剰になったり低下したりすることで体温調節や血流が乱れ、神経が異常な感覚を発するためです。糖尿病以外の病気が背景にある可能性も否定できません。
皮膚疾患や感染症
足の裏の熱さは、皮膚のトラブルや感染症が原因となることもあります。例えば水虫(白癬)はかゆみや皮むけだけでなく、炎症を伴って熱さを感じることもあります。小さな傷や皮膚の炎症でも、局所的に熱を持ってしまうことがあります。
糖尿病による3大合併症
糖尿病は、自覚症状がないまま病気が進行してしまい、3大合併症を引き起こす恐れがあります。健診などで高血糖(血糖値の異常)を指摘された場合は、早めに適切な治療を始めましょう。糖尿病による3大合併症は、以下の通りです。
糖尿病網膜症
糖尿病による血管障害で、網膜の毛細血管に障害が起こって視力が低下する病気です。末期になるまで自覚症状がないまま進行することが特徴です。病状が進むと眼底出血を起こして失明に至ることがあります。
糖尿病腎症
自覚症状が乏しいまま進行するため、腎不全を引き起こして腎臓透析となることがあります。国内における人工透析導入の約半数の原因が、糖尿病腎症となっています。
糖尿病神経障害
糖尿病による神経障害で、立ち眩みや排尿障害・排便障害・EDなどが起こり、末梢神経障害では足の痺れや冷感、足のつりなどが起こります。足の病変としては、感覚低下や潰瘍・足壊疽などを引き起こします。
動脈硬化(大血管障害)を
引き起こすリスク
糖尿病が長引くと、動脈硬化が進行して心筋梗塞や脳梗塞などを起こすリスクを高めてしまいます。症状が現れた時には、すでに重篤な状態となることが多いため、高血糖や高血圧、脂質異常などを指摘された場合は、早期から治療を行うことが重要です。
なお、現在、糖尿病の治療に用いられる薬は、動脈硬化に効果が期待できるとされる「SGLT2阻害薬」をはじめ、「GLP-1受容体作動薬」「BG剤(ビグアナイド)」などがあります。
糖尿病の検査
糖尿病の有無を確認するには、血糖値やHbA1cを検査します。糖尿病は、初期における自覚症状がないため、定期的に検査することが重要です。
血糖値
 血糖値は、血液中のぶどう糖の値を指し、糖尿病コントロールの指標とされています。糖尿病には、食前の血糖値または食後の血糖値が高い場合のほか、食事前後の両方が高い場合などタイプが分類されます。また、食後の血糖値の上昇は心臓病や脳卒中への影響が注視され、食前だけではなく食後の血糖値コントロールも重要とされています。
血糖値は、血液中のぶどう糖の値を指し、糖尿病コントロールの指標とされています。糖尿病には、食前の血糖値または食後の血糖値が高い場合のほか、食事前後の両方が高い場合などタイプが分類されます。また、食後の血糖値の上昇は心臓病や脳卒中への影響が注視され、食前だけではなく食後の血糖値コントロールも重要とされています。
HbA1c
 HbA1cとは、血糖値が上がることでぶどう糖が赤血球のヘモグロビンと結合したものを言います。このため、血糖値が高くなるとHbA1c値も高くなります。HbA1c値は、糖尿病合併症の進行に大きく関与しているため、NGSP値が7.0%未満へのコントロールが目安となっています。
HbA1cとは、血糖値が上がることでぶどう糖が赤血球のヘモグロビンと結合したものを言います。このため、血糖値が高くなるとHbA1c値も高くなります。HbA1c値は、糖尿病合併症の進行に大きく関与しているため、NGSP値が7.0%未満へのコントロールが目安となっています。
隠れ糖尿病とは
糖尿病であるのに、空腹時血糖値(スクリーニング検査)の数値に現れない糖尿病を隠れ糖尿病と言います。この場合、前日夜から絶食して空腹状態で健康診断などを受けると、空腹時血糖値は下がりますが、HbA1cだけは影響されないため食後高血糖が反映された状態となり、空腹時血糖値だけで見落とされ、隠れ糖尿病となります。
著書紹介:渡邊 智 院長
 秋田大学医学部卒業後、横浜労災病院内分泌糖尿病センターや東京女子医科大学病院などで、糖尿病・高血圧・甲状腺疾患を中心とした最先端の診療に従事。 現在は東伏見駅前内科糖尿病クリニックの院長として、高度医療機関で培った知見を地域へ還元している。「糖尿病」と「内分泌」の専門医として、専門的な管理から日常的な不調まで、患者一人ひとりに寄り添ったきめ細やかな診療を行う。
秋田大学医学部卒業後、横浜労災病院内分泌糖尿病センターや東京女子医科大学病院などで、糖尿病・高血圧・甲状腺疾患を中心とした最先端の診療に従事。 現在は東伏見駅前内科糖尿病クリニックの院長として、高度医療機関で培った知見を地域へ還元している。「糖尿病」と「内分泌」の専門医として、専門的な管理から日常的な不調まで、患者一人ひとりに寄り添ったきめ細やかな診療を行う。
資格・学会
- 日本糖尿病学会糖尿病内科専門医
- 日本内分泌学会内分泌代謝科(内科)専門医
- 日本内科学会 認定内科医